炭素税とは?導入が求められる背景、メリット、海外の事例も紹介
炭素税とは、石油・石炭・天然ガスなどの二酸化炭素を排出する燃料や、電気の使用量に応じて、企業・個人に課せられる税金のことです。この記事では、炭素税について知りたい人に向けて、炭素税の概要や仕組み、必要とされる背景、メリット・デメリットなどについて解説します。諸外国の導入事例や日本の動向も解説するため、ぜひ役立ててください。
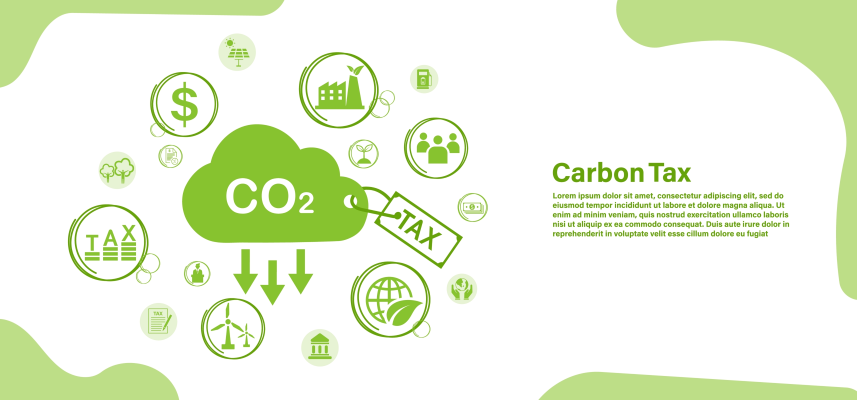
炭素税とは何か
炭素税とは、二酸化炭素を排出する燃料(石油・石炭・天然ガスなど)や電気を使用した際、その使用量に応じ、課せられる税です。環境税の一種で、日本ではまだ導入されていません。以下では、炭素税が導入されている国を紹介します。
炭素税が導入されている国
炭素税を最初に導入したのはフィンランドで、1990年に導入されました。その後、1991年、1992年にスウェーデンとデンマークで導入され、現在ではスイス、アイルランド、フランス、ポルトガル、カナダ、ドイツなど欧州を中心に導入が進んでいます。
カーボンプライシングとは?
カーボンプライシングとは、炭素に価格をつけることで、排出者の行動を変えさせる政策手法です。炭素税はカーボンプライシングの内の1つでもあります。またカーボンプライシングは、明示的カーボンプライシングと暗示的炭素価格の2つに分類されます。以下では、それぞれの特徴について解説します。
明示的カーボンプライシング
明示的カーボンプライシングは、炭素の排出量に応じて直接価格をつける仕組みです。炭素税のほかに「排出量取引制度」があります。排出量取引制度は、排出者の一定期間内の温室効果ガス排出量に制限を設け、排出者同士の取引も認める制度のことです。
排出量取引制度において、用いられる手法の1つがカーボンクレジットです。カーボンクレジットは、企業間で、二酸化炭素をはじめとした温室効果ガス排出削減量を売買できる仕組みを意味します。
※参考:資料5議題5(CP意義)
暗示的炭素価格
暗示的炭素価格とは、消費者や生産者に対して間接的に、排出量削減の価格を課す仕組みのことです。暗示的炭素価格の代表的な手法は、以下の通りです。
・エネルギー課税化石燃料などに対する課税
・補助金、税制優遇特定の製品や施設などに対する補助金や税制優遇
・固定価格買取制度電気事業者に対して、特定の価格や期間、条件で再生可能エネルギー由来の電気の買取を義務付けるもの
また、2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」をもとに、建築物省エネ法が改正されました。これにより、原則全ての新築住宅や非住宅に対して、省エネ基準適合が義務付けられます。2025年4月に施行される予定です。
※参考:資料5議題5(CP意義)
炭素税の仕組み(課税段階)
課税段階は、4パターン、またはそれらの組み合わせとすることが考えられます。以下では、4パターンの課税について解説します。
・上流課税化石燃料の採取・輸入する時点での課税
・中流課税化石燃料製品や電気の製造所から出荷する時点での課税
・下流課税化石燃料製品、電気の需要者へ供給される時点での課税
・最下流課税最終製品が最終消費者に供給される時点での課税
※参考:210301資料2(セット版)
炭素税が必要とされる背景
炭素税の導入が求められる背景には、地球温暖化があります。フランス国立科学研究センターによると、このまま温暖化が進めば、2100年には世界の平均気温が最大で5.8度上昇するといわれています。そこで、地球温暖化を防止するためには、二酸化炭素など温室効果ガスの削減が必要です。
2015年のパリ協定にて、参加各国は二酸化炭素の削減目標を出し5年ごとに提出、更新が義務付けられています。また日本もその一翼を担い、二酸化炭素の排出量を2030年までに2013年比で26%減らす目標を掲げています。
炭素税を導入するメリット・効果は?
二酸化炭素排出量に応じて化石燃料に炭素税をかけることによって、環境負荷が大きいものと小さいもので価格差が生まれるようになります。これによって環境への影響を理解し、地球温暖化の抑制や二酸化炭素削減の必要性に気づき、環境問題について企業や消費者が知るきっかけになるでしょう。企業や家庭の省エネにつながる点も、炭素税を導入するメリットです。
炭素税の導入にデメリットはある?
炭素税を導入することで、企業の生産活動、成長を妨げる可能性があります。日本は、化石燃料を輸入に頼っているため、炭素税が上乗せされると、さらにコストが上昇します。また、炭素税の導入がない国に対して価格上のハンデを負うため、国際的競争力が低下する恐れもあるでしょう。
低所得者の負担が増加する可能性がある点も、炭素税を導入するデメリットとして挙げられます。
諸外国の炭素税導入事例
炭素税について理解を深める際には、導入事例を把握することが大切です。ここでは、諸外国の炭素税導入事例を紹介します。
フィンランド
フィンランドは、1990年に世界で初めて炭素税を導入しました。その後1997年と2011年にエネルギー税制改革を実施し、所得税の減税、企業の社会保障費削減による税収の減少分を一部、炭素税収で補填しています。
税収の推移は、「諸外国における炭素税等の導入状況」によると、2014年に1,051百万EUR、2015年に1,119百万EUR、2016年に1,233百万EURとなっています。
※参考:諸外国における炭素税等の導入状況
スウェーデン
スウェーデンは、1991年に炭素税の導入と、法人税の大幅減税をする環境税制改革を実施しました。この取り組みによって、二酸化炭素排出の削減とGDP成長の両立を達成し、環境と経済を切り離すことに成功しました。
税収の推移は、「諸外国における炭素税等の導入状況」によると、2010年に270億SEK、2011年に254億SEK、2012年に253億SEKと続いています。2013年から2016年にかけては、240億SEKから246億SEKの範囲で推移していることが分かります。
※参考:諸外国における炭素税等の導入状況
デンマーク
デンマークは1992年にCO2税を導入し、最初は産業部門に対して大幅な軽減税率が適用されていましたが、2010年になって税率を一本化しました。2010年以降は、毎年の税率(引上げ)が、インフレ率に応じて自動設定されています。
税収の推移は、「諸外国における炭素税等の導入状況」によると、2010年に57.6億DKK、2011年に59億DKK、2012年に56.8億DKKと続いていることが分かります。その後、2013年から2016年までの範囲では、36.2億DKKから37億DKKの間で推移しています。
※参考:諸外国における炭素税等の導入状況
スイス
スイスは、2008年に炭素税を導入し、輸送用燃料を除く化石燃料に課税しています。将来の税率は、過去の排出実績に基づいて算定され、2018年時点では84~120CHF/tCO2が適用されています。
税収の推移は、「諸外国における炭素税等の導入状況」によると、税収の推移は、2012年に5.52億CHF、2013年に6.42億CHF、2014年に7.58億CHF、2015年に8.27億CHFと示されています。
※参考:諸外国における炭素税等の導入状況
アイルランド
アイルランドは、経済危機からの再建を図る一環として、2010年に炭素税を導入しました。炭素税の税収は、一般会計に取り入れられ、2010年以降の財政改善に寄与しています。その後、2013年からは石炭にも炭素税が課税されました。
税収の推移は、「諸外国における炭素税等の導入状況」によると、2010年に223百万EUR、2011年に298百万EUR、2012年に354百万EURと増加しています。その後、2013年から2015年にかけても増加が続いていることが分かります。
※参考:諸外国における炭素税等の導入状況
フランス
フランスは、2014年4月に、経済危機からの回復と環境保護を目指し、化石燃料に関連する内国消費税を炭素成分とその他成分に再構成する形で、炭素税を導入しました。税率は、段階的に引上げられており、2030年にはCO2排出量1トン当たり100ユーロに達する予定です。
また、炭素税収の大部分は、競争力の維持や雇用促進のための所得税や法人税の控除、交通インフラグリーン化への資金調達、エネルギー移行に寄与するプロジェクトなどに充てられています。
※参考:諸外国における炭素税等の導入状況
ポルトガル
ポルトガルは、2015年に環境に配慮した税制改革の一環として、炭素税を導入しました。税率は前年度のEU-ETS制度における排出枠価格の年間平均値に基づいています。
環境税制改革の事前評価によると、2015年の炭素税の税収額は95百万EURと見込まれており、環境税制改革全体の税収規模は165.5百万EURとなります。導入以降は、エネルギー税との合算値のみ公表されるため、炭素税単独の税収額は明らかになっていません。
※参考:諸外国における炭素税等の導入状況
日本で打ち出された「成長志向型カーボンプライシング構想」とは
成長志向型カーボンプライシング構想は、「成長志向型」とある通り、企業がGXに積極的に取り組むための仕組みです。規制と先行投資支援を組み合わせて、排出削減と産業競争力向上、経済成長を促進します。
GXとは、温室効果ガスを発生させる化石エネルギーから、太陽光発電、風力発電などのクリーンエネルギー中心へと転換する取り組みを指します。GXは、Green Transformation(グリーントランスフォーメーション)の略称で、2023年2月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」に基づいています。
日本の産業競争力強化・経済成長の促進のためには、さまざまな分野への投資が必要で、その規模は今後10年間で150兆円を超えるとされています。この膨大なGX投資を実現するために、官民が協力して推進するためのアプローチとして、「成長志向型カーボンプライシング構想」が打ち出されました。
まとめ
炭素税は、二酸化炭素を排出する燃料(石油・石炭・天然ガスなど)や、電気を使用した際の使用量に応じて、課せられる税を指します。日本ではまだ導入されていませんが、フィンランドやスウェーデン、デンマークなど多くの国で導入されています。
株式会社ユポ・コーポレーションは、合成紙「ユポ」の製造販売を行っています。高い機能性を備えながらも、環境負荷の少ない点が、合成紙「ユポ」の強みです。国内No.1のシェア※を誇り、50年以上の実績があります。またユポは、セキュリティラベルの基材としても良く活用されています。転移タイプ・非転移タイプ・ぜい質タイプ、それぞれに向いた特性のラインナップがあることが特徴です。
※...合成紙市場における販売量(t)、(参考)矢野経済研究所「2022年版 特殊紙市場の展望と戦略」
「ユポ」は、脱プラスチックが難しい場合でも、プラスチック削減に貢献できる素材です。「ユポグリーン」シリーズは植物由来樹脂を配合しています。どちらも化石燃料由来のプラスチック使用量やCO₂排出量の削減につながる「環境負荷削減に貢献できる素材」としておすすめします。環境に配慮した素材をお求めの際は、ぜひお問い合わせください。
※「ユポ」「ユポグリーン」は株式会社ユポ・コーポレーションの登録商標です。
この記事を書いた人株式会社ユポ・コーポレーション
地球と人を大切にしていきたい。
当社はこれからも環境保全や環境負荷の削減を使命として社会に貢献していきます。



