ハザードマップの作り方とは|種類や活用のポイント、今後の課題についても解説
近年、地震や台風など、さまざまな自然災害が発生しており、防災対策への意識が高まっています。ハザードマップを作ることは、防災対策の1つです。この記事では、ハザードマップの作り方について解説します。ハザードマップの種類や活用するポイント、課題についても解説するので、参考にしてください。
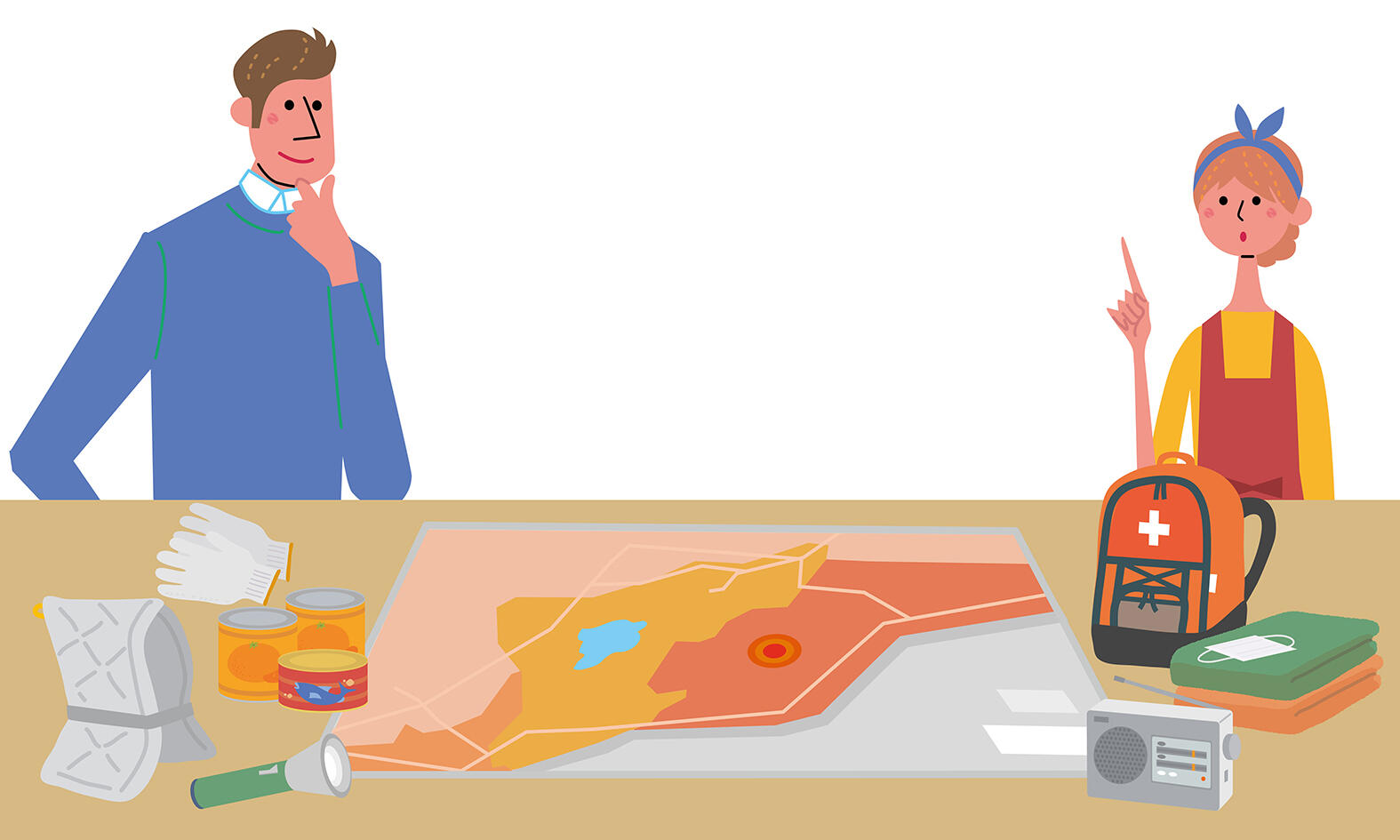
ハザードマップとは
ハザードマップとは、災害が発生した際の避難場所や避難経路、危険な場所についての情報をまとめた地図です。各自治体が災害の種別ごとに作っています。事前に災害に対するリスクを把握できるため、自然災害による被害の軽減や防災対策に使われています。
ハザードマップは、市区町村役場の窓口やホームページ、国土交通省のハザードマップポータルサイトなどから入手できます。
ハザードマップと防災マップは目的が違う
ハザードマップと防災マップは、似ていることから混同されがちですが、それぞれ目的が違います。防災マップは避難時だけではなく、事前の避難計画や被災後の対応に役立てることを目的としています。そのため防災マップには災害時の避難場所や一次集合場所の他、給水ステーションなど防災活動拠点や設備が示されています。
ハザードマップは、災害による被害の予測図であり、記載する情報は災害の種別ごとに異なります。災害発生時の危険を回避することを主な目的としています。
ハザードマップの種類と特徴
ハザードマップは、災害の種類ごとに記載する内容が異なります。ここでは、9つのハザードマップについて解説します。
洪水ハザードマップ
洪水ハザードマップとは、大雨で河川が氾濫した際の洪水リスクを示す地図です。洪水が発生しやすい河川や場所、洪水による浸水範囲や深さ、避難場所や避難経路などが記載されています。国土交通省は、2021年2月に中小河川も、洪水ハザードマップの作成対象として義務化する方針を示しました。対象河川は、従来の約2,000から約15,000に増加する見込みです。
内水ハザードマップ
内水ハザードマップとは、大雨による排水用の水路や小河川、下水道からの浸水リスクを示す地図です。浸水が予想されるエリアに内水氾濫の危険性を知らせるとともに、避難所に関する情報なども記載されています。内水氾濫は、大雨などで下水道の流入量が排水能力を超えてしまい、川へ放流しきれずに浸水することで、地中に水がしみこみにくい都市部で発生しやすい災害です。
津波ハザードマップ
津波ハザードマップとは、津波発生時のリスクを示す地図です。津波被害の恐れがある地域ごとに、想定される地震や津波の規模に応じて作られます。津波ハザードマップには、津波被害の範囲や浸水被害の深度、施設の危険度などが記載されています。
高潮ハザードマップ
高潮ハザードマップは、高潮発生時の浸水を想定した地図を指し、高潮が発生した際の浸水範囲や到達する高さが記載されています。高潮とは、台風や低気圧の接近により海水が吸い上げられ、海面の水位が高くなる現象です。低い土地は浸水する恐れがあり、高潮と満潮の時間が重なると、さらに被害が大きくなります。
高潮は海岸付近のみならず、河川に沿って内陸に遡上するケースもあり、海に面していない市区町村でも、高潮ハザードマップを作っている場合があります。高潮が想定されない内陸の自治体では作られていません。
ため池ハザードマップ
ため池ハザードマップとは、大雨でため池が決壊した際の浸水リスクを示した地図で、浸水の区域や深さ、避難場所などが記載されています。ため池とは、農業用水として使うために水を蓄えている人工池のことです。ため池ハザードマップは、農業が盛んな地域やため池が多い地域で作られ、農業用ため池がない都市部では作られていません。
土砂災害ハザードマップ
土砂災害は大きく分けると、がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)、土石流、地滑りの3種類です。土砂災害ハザードマップには、土砂災害のリスクや避難情報が記載され、市町村が土砂災害防止法第8条第3項に基づいて作ります。
また、地形や地質情報などから、土砂災害が発生する可能性がある、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」が記載されています。
土砂災害警戒区域には、土砂災害で住民の生命、または身体に危害が生じる恐れがある区域が指定されています。土砂災害特別警戒区域は、土砂災害で建築物の損壊が生じ、住民に著しい危害が生じる恐れがある区域で、広告や売買契約には都道府県知事の開発許可が必要です。
土砂災害警戒区域がない自治体は、土砂災害ハザードマップを作りません。
地震ハザードマップ
地震ハザードマップとは、大規模地震が発生した際のリスクを示す地図です。地震の揺れの強さや建物倒壊の度合い、液状化のような地盤被害について記載されています。液状化現象が発生すると、ライフラインへの被害だけでなく、宅地周囲に段差が生じて、住み続けられないこともあります。
地震ハザードマップには、想定される建物被害の割合や棟数などが示されている場合もあります。自治体により、想定する地震や被害の規模、表示方法が異なる場合もありますが、揺れやすい地域の目安にもなります。
火山ハザードマップ
火山ハザードマップとは、火山を原因として発生する火砕流や噴石の落下、土石流、火山性ガス、融雪型火山泥流など、噴火により被害が予想される範囲と、避難すべき地域や避難場所が記載された地図です。噴火によるリスクには、噴煙や降下火山灰による広範な被害や火災などがあります。
日本は世界有数の火山国であり、111の活火山があります。火山ごとにハザードマップが作られており、噴火の規模によっては、火山から離れた地域にも被害が出る恐れがあります。
大規模盛土造成地マップ
大規模盛土造成地マップとは、造成地の変動予測と危険度を示す地図です。造成前後の地形図を重ね合わせて、大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を示しています。
大規模盛土造成地は、谷や沢を埋め立てたり、斜面を盛り土により造成したりなど、一定規模以上の造成地のことです。大雨や地震発生時に滑動崩落が生じ、地滑りやがけ崩れ、土砂流出が発生する恐れがあるため、当該地や下流域に大きな被害が生じるリスクがあります。
※参考:大規模盛土造成地マップ|兵庫県
ハザードマップを活用するポイント
ハザードマップは、災害被害の軽減や防災対策に重要ですが、活用方法を把握していない人も多いようです。ここでは、4つの活用ポイントを解説します。
災害リスクを把握して事前準備をする
ハザードマップは、自宅や会社がある地域に、どのような災害リスクがあるのかを把握するために役立つ地図です。災害リスクの種類やリスクの高さは、地形により異なります。災害リスクを把握できれば、災害の危険度が高い場所に自宅や会社があっても、事前に避難準備ができたり、早めの避難行動につながったりします。
災害発生時の避難ルートや避難場所を把握する
ハザードマップを活用できれば、事前に自宅や会社から避難場所までの避難ルートを確認できます。実際に災害が起きてから、むやみに動いては危険です。ハザードマップは、異常や災害等の発生状況に応じて、自治体や個々人が避難判断をしなければならない際に役立ちます。
通行止めの可能性を確認する
ハザードマップには、道路防災情報を提供している地図もあり、土砂崩れや冠水などで道路が寸断されやすい場所を、事前に把握できます。事前に避難ルートを把握する際には、自宅や会社の周辺で通行止めが発生しやすい道路を確認しましょう。避難ルートは、1つだけではなく複数把握することが大切です。
紙のハザードマップを用意する
Webサイトのハザードマップは、パソコンやスマートフォンで見られて便利です。しかし、災害発生時に停電したり、アクセスが集中したりすると、Webサイトのハザードマップは見られなくなる恐れがあります。災害に備えて、事前にプリントアウトし、紙のハザードマップを手元に置いておくと安心です。
ハザードマップの作り方
ハザードマップはどのような流れで作るのでしょうか。ここでは、土砂災害ハザードマップを例に、作り方を解説します。
※参考:土砂災害ハザードマップ作成ガイドライン|国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課
1.資料を収集・整理する
土砂災害ハザードマップを作る際には、市町村地域防災計画や地区防災計画、基図、土砂災害警戒区域の情報などの資料を収集し、整理します。市町村地域防災計画や地区防災計画は、土砂災害警戒区域や土砂災害に関する情報の伝達方法や、避難場所などを指します。
基図とは、基礎調査に使用した図面や1/2,500の数値地図などです。土砂災害警戒区域の資料には、土砂災害警戒区域の法指定図(公示図書)や、基礎調査結果(区域調書)などが記載されています。
2.地区単位や避難単位を設定する
同一の避難行動をとるべき地区単位や避難単位を設定します。市町村内に安全な避難場所がなく、市町村や都府県を越えた住民の避難が必要な場合は、市町村間や都府県間で事前調整を図る必要があります。
3.基図を作る
土砂災害ハザードマップに使う基図は、ハザードマップの作成単位や使う地図の縮尺などを考慮しましょう。国土地理院の電子国土基本図や、基礎調査に使った数値地図などから選ぶことをおすすめします。
4.支援や協力を求める
市町村は、土砂災害ハザードマップを作るにあたり、国や都道府県に技術的助言を求めましょう。それにより、基礎調査結果による土砂災害警戒区域の区域図や自然現象の種類を、基礎資料として提供してもらえます。
5.共通項目と地域項目を記載する
土砂災害ハザードマップには、共通項目と地域項目を記載します。共通項目とは、土砂災害防止法第8条第3項に基づき、円滑な警戒避難を確保するうえで必要不可欠な最小限の項目のことで、全ての土砂災害ハザードマップに記載されています。地域項目とは、「共通項目」以外で地域の特性や実情に応じた項目です。
6.記載内容を更新する
全てのハザードマップは、作って終わりではありません。土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域、避難場所など、記載内容に変更があった場合には、その都度更新しましょう。
ハザードマップにおける課題
ハザードマップはうまく活用できないと、効果が期待できません。ここでは、3つの課題について解説します。
ハザードマップの認知が低い
自然災害に対して危険性を感じていない人や、近所付き合いの少ない年代は防災意識が低い傾向にあります。防災意識の低い人のなかには、ハザードマップを見たことがない人もおり、認知が低いといえます。
住民の防災意識が低い
ハザードマップを認知していても、住民の防災意識が低いと、避難に対する認識が薄かったり、避難行動をとらなかったりします。また、災害に対する危険性や避難所へ行く必要性について、理解できていない場合もあります。
障害のある人や外国人に対応したハザードマップが少ない
自治体の多くでは、障害のある人に向けたハザードマップを作っていません。作っていても、多くは視覚障害者向けの「音声案内」や「点字」によるものです。視覚以外の障害がある人に向けた伝達方法は、さらに少ないといえます。外国人向けのハザードマップは、国籍や母国語に合わせて作る自治体が少しずつ増えてきました。
ハザードマップには合成紙「ユポ」がおすすめ
ハザードマップは、合成紙「ユポ」で作ることをおすすめします。合成紙「ユポ」は、プラスチックフィルムと紙の特徴を併せ持ち、高い機能性を備えながらも、環境負荷を削減できる合成紙です。耐水性や耐久性、耐油性に優れており、水に強く破れにくい点がメリットといえます。
合成紙「ユポ」でハザードマップを作れば、大雨が降る環境でも広げて見ることができ、ふやけたり破れたりする心配がありません。何度も折りたたんだり、使い込んだりしても、ボロボロになりにくい点も強みといえます。
まとめ
ハザードマップを作ることは、地震や台風などの自然災害が多く発生している近年において、大切な防災対策の1つです。自治体は、災害発生時の危険を回避するためにも、各種ハザードマップを作り、必要に応じて記載内容を更新していきましょう。
株式会社ユポ・コーポレーションは、合成紙「ユポ」の製造販売を行っています。高い機能性を備えながらも、環境負荷の少ない点が、合成紙「ユポ」の強みです。国内No.1のシェア※を誇り、50年以上の実績があります。ハザードマップを作ろうと検討している自治体は、ぜひ資料をご覧ください。
※...合成紙市場における販売量(t)、(参考)矢野経済研究所「2022年版 特殊紙市場の展望と戦略」
「ユポ」は、脱プラスチックが難しい場合でも、プラスチック削減に貢献できる素材です。「ユポグリーン」シリーズは植物由来樹脂を配合しています。どちらも化石燃料由来のプラスチック使用量やCO₂排出量の削減につながる「環境負荷削減に貢献できる素材」としておすすめします。環境に配慮した素材をお求めの際は、ぜひお問い合わせください。
※「ユポ」「ユポグリーン」「ユポエアー」は株式会社ユポ・コーポレーションの登録商標です。
この記事を書いた人株式会社ユポ・コーポレーション
地球と人を大切にしていきたい。
当社はこれからも環境保全や環境負荷の削減を使命として社会に貢献していきます。



