ヤング率とは? 応力・ひずみとの関係や材料ごとの値を一挙紹介
ヤング率とは、素材としての物質の剛性、弾性を示す値です。三次元の物体についての構造解析や耐荷重の計算において、素材のヤング率は欠かせません。ひずみや応力との関係やそれぞれの定義、材料ごとのヤング率をご紹介します。
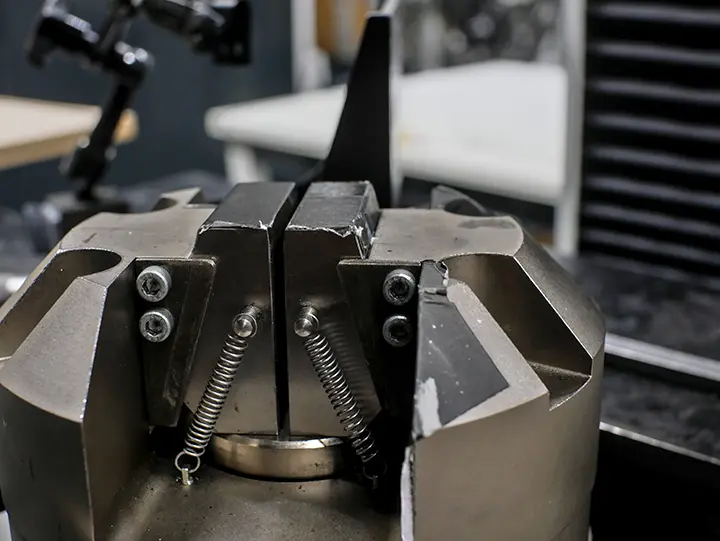
ヤング率とは、一方向への力と同方向への変形量の比
ヤング率とは、縦弾性係数とも呼ばれ、一方向への応力と同方向への変形量(ひずみ)の比を表す値です。材料の硬さ、変形のしにくさを表すものです。
ヤング率はフックの法則におけるバネ定数になぞらえて解説されます。両者を比較すると以下のようになります。
フックの法則 F=kx
F:力(N)x:伸び(m)k:バネ定数(N/m)
ヤング率 σ=Eε
σ:引張応力(N/㎟)ε:ひずみ E:ヤング率
ヤング率がひずみと応力の比例関係を表していることが分かります。
ヤング率の求め方(計算式・単位)
あらためてヤング率の式を見てみましょう。
σ=Eε
この式を変形したものを以下に示します。
E=σ/ε
つまりヤング率は、引張応力をひずみで割った値です。
応力は圧力と同様に単位面積当たりの力であり、ひずみは特定方向の変化量を元の長さで割ったもの、その方向において物体が変形した割合を示す値と考えられます。ひずみが無単位であるため、ヤング率の単位は、応力と同じでN/㎟です。
ヤング率と各用語(応力・ひずみ・ポアソン比)との違い
ヤング率の解説には、応力、ひずみ、ポアソン比などの用語が用いられます。応力やひずみは測定値ですが、ヤング率とポアソン比は素材ごとに決まる物性値です。
これらの用語の定義や意味があいまいなままでは、ヤング率の理解も深まりません。応力、ひずみ、ポアソン比の意味と定義を解説します。
応力|面積当たりの抵抗力
応力とは、物体が力を加えられて変形したときに元の形状に戻ろうとする抵抗力を、その向きに垂直な断面積で割った値です。計算式は以下の通りで、力の単位にはN(ニュートン)を用い、断面積は㎟で表します。
σ=F/S
σ:応力(N/㎟) F:外力(N) S:断面積(㎟)
ヤング率は引張荷重に対しての値で、応力は引張応力です。力の方向によって、圧縮応力や曲げ応力、せん断応力も存在します。
応力は3次元の剛体を扱う際に重要な測定値であり、材料力学や構造力学において重要な働きをします。
ひずみ|外力による弾性変形の度合い
物体の多くは、力を加えられると変形します。例えば、フックの法則は物体を一次元的に捉えて力と変形量が比例することを示す法則です。
物体は三次元体であり、外力によって空間的に変形します。ひずみは、物体の変形に対して外力が与えられた方向に対する変形量を測定し、その方向の長さに対する変形の割合を求めたものです。以下の式で表されます。
ε=ΔL/L
ε:ひずみ ΔL:外力と平行な方向の変形量 L:外力と平行な方向の長さ
LとΔLの単位は㎜をはじめとする長さですが、商であるひずみは無単位です。
ポアソン比|縦横のひずみにおける比率
現実の物体は三次元です。三次元の物体は一方向に引っ張られると伸び、伸びた物体は細くなります。太いゴムを引っ張った状態のイメージです。
このとき、縦のひずみεと、横のひずみε'の比率を表した値がポアソン比です。
ν=ε'/ε
ν:ポアソン比 ε':横のひずみ ε:縦のひずみ
荷重変形に対して体積が一定の素材のポアソン比は0.5で、天然ゴムはこれに近い値をとります。一般的な金属のポアソン比は0.3程度です。
材料が等方性弾性体であれば、ヤング率やポアソン比から横弾性係数が求まり、横方向のひずみやせん断応力を考慮できます。横弾性係数の計算式を以下に示します。
G=E/2(1+ν)
G:横弾性係数 E:ヤング率 ν:ポアソン比
材料ごとのヤング率
ヤング率は、物質の一方向荷重への変形のしにくさを表します。これは物質の素材ごとに数値が決まっている物性値です。構造計算や設計では、ヤング率の値を基に構造物の応力や荷重を解析します。
主な材料のヤング率
主な材料のヤング率をご紹介します。単位はGPa(ギガパスカル)です。
|
種類 |
材質 |
ヤング率 |
|
金属 |
アルミ |
66.7 |
|
非金属 |
ガラス |
71.6 |
|
金属 |
チタン |
106 |
|
金属 |
マグネシウム |
44.7 |
|
金属 |
鉄 |
211.4 |
|
合金・鋼材 |
ステンレス |
193 |
|
合金・鋼材 |
アルミ合金 |
70 |
|
樹脂 |
シリコン |
193 |
|
樹脂 |
プラスチック |
0.7~4.0 |
|
繊維 |
ナイロン |
0.12~0.29 |
|
木材 |
ヒノキ |
13 |
樹脂のヤング率は含有成分や種類によって変化します。
ヤング率が大きいほど剛性がある
ヤング率は、素材の剛性を示す値とも考えられます。これは、公式のσ=Eεから分かるように、Eが大きいとひずみを生じさせるうえで大きな応力が必要となるためです。
一般に、金属や鉱物類、セラミックなどがヤング率が大きな素材です。
剛性を保ちたい部品、強い荷重に対してできるだけ変形を抑えたい部位などにヤング率の高い素材が採用されます。ただし、剛性が高いために脆く欠けやすい性質を持つ素材もあり、ヤング率のみでは用途に適した素材かどうかは判断できません。
ヤング率が小さいほどしなやかさがある
ヤング率が小さい物質は、柔軟性やしなやかさを持つ素材です。荷重に対しての変形量が大きいものの、衝撃の吸収や荷重を分散させる効果が期待できます。
ヤング率が小さい素材は、ゴムや樹脂、木材などです。これらの素材は、弾力性に富み、しなやかさを持っています。
柔軟性がある素材は割れや欠けなどの破損、欠損のリスクが小さい点が特徴です。連続して強い荷重がかかる部位にヤング率の小さい素材を採用すると、力を分散して全体の破損リスクを下げられます。
「ユポ」はしなやかで適度な剛性がある
ユポは、紙のような手触りを持ちながら、しなやかさと剛性(紙コシ)や強度を併せ持つ素材です。合成樹脂のポリプロピレンと無機充填材に少量の添加剤を加えて、二軸延伸フィルム成形法で、内部にミクロボイドと呼ばれる微細な空孔を発生させて成膜する手法でつくられます。
二軸延伸することで適度な剛性、弾性を発揮しつつ、表面処理によるすぐれた印刷特性を実現しています。
まとめ
ヤング率について解説しました。ヤング率は力に対する変形量の比で、材質のヤング率を知れば硬さや柔らかさがわかります。各材料のヤング率を知り、適切なものを選べるようになりましょう。
また、ユポは剛性(紙コシ)と柔らかさをあわせ持つ素材です。ユポについて興味のある方はぜひ下記をご覧ください。
ユポの全体像が3分でわかる資料を見る
ユポについて詳しく知りたい方はこちら
※「ユポ」は、株式会社ユポ・コーポレーションの登録商標です。
この記事を書いた人株式会社ユポ・コーポレーション
地球と人を大切にしていきたい。
当社はこれからも環境保全や環境負荷の削減を使命として社会に貢献していきます。



