垂れ幕に適した素材とは?屋内・屋外用の素材の特徴・メリット・選び方などを徹底解説
垂れ幕の製作をする際には、素材選びが重要です。垂れ幕用の素材は多種多様であり、使用用途に合わせて異なる素材を選ぶ必要があります。この記事では、垂れ幕に適した素材を屋内用・屋外用に分けて解説します。素材ごとのメリット・デメリットや、垂れ幕の用途別に素材の選び方などを解説するため、ぜひ参考にしてください。
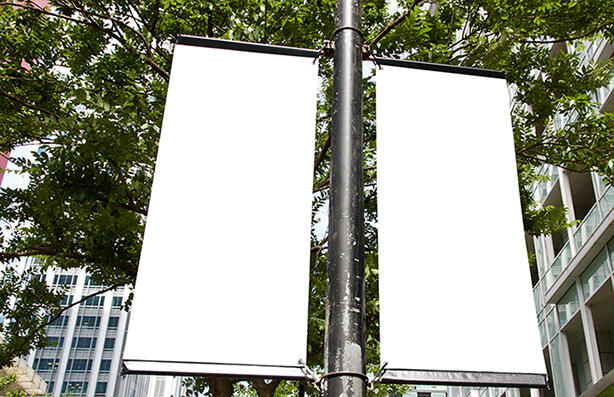
垂れ幕に使われる素材とは?
垂れ幕によく使われる素材は、主に布系と塩化ビニール系の2種類です。
布系の素材としては、ポリエステルの織布がよく採用されます。布系はポリエステル以外の素材もあり、シワになりにくい、軽い、折りたたんで持ち運びしやすい、といった特徴が魅力です。
塩化ビニール系は、布系の素材を塩化ビニール樹脂で加工したものです。厚みがあり、耐久性にも優れています。また、発色がきれいで高級感があるのもポイントです。
屋内の垂れ幕に向く3つの素材
屋内で利用する垂れ幕に向いている素材は、トロマット、ポンジ、コットンなどの布系の素材です。以下では、それぞれについて解説します。
切りっぱなしで使えるトロマット
トロマットとは、ポリエステル糸を平織りした厚手の布系の素材です。しわになりにくく、折りたたんで持ち運びや保管ができます。裁断してもほつれないため縫製する必要がなく、切りっぱなしで使用可能です。屋内で使われる垂れ幕(タペストリー、応援幕、イベント幕など)によく使われています。3か月から半年程度までの短い期間なら、屋外でも使用できます。
両面使えるポンジ
ポンジとは、ポリエステル糸を平織りした薄い布系の素材です。薄くて絵柄が裏からも透けて見えるため、両面使用できます。ただし、裏から見ると文字や柄は逆さまになります。軽くてなびくため、のぼりとして使用される場合が多いです。薄くて強度は低く、長期間の使用には向いていません。ただし、短期間なら屋外でも使用可能です。
和のテイストが出せるコットン
コットンとは、木綿糸を織った布系の素材です。染技術を併用すれば、伝統的な和風の垂れ幕の演出ができます。シャークスキン生地、カツラギ生地、天竺木綿、帆布などがあり、種類が豊富です。ただし、雨に濡れると水を吸い込む性質があるため、屋外での使用は向いていません。
屋外の垂れ幕に向く素材
屋外でよく利用される垂れ幕の素材として、塩化ビニール系のターポリンがあります。以下でくわしく解説します。
垂れ幕として人気の高いターポリン
屋外用の垂れ幕の素材として、ターポリンがよく使用されています。耐久性が高く、雨や汚れにも強いです。ターポリンは、ポリエステルの布地を塩化ビニール樹脂で挟みこんだ複層構造になっています。印刷方法は、インクジェット印刷が用いられる場合が多いです。ただし、異樹脂を組み合わせているため、樹脂原料としてリサイクルすることは難しい特徴があります。
垂れ幕に布系素材を使うメリット・デメリット
メリット
薄くて軽い布系素材を選択すれば、軽量な垂れ幕を作成できます。持ち運びや保管に便利で、メリットといえるでしょう。また布系素材は種類が多く、天然素材も選択できます。
デメリット
布系素材は屋外での長期的な使用には向いていません。特に、吸水性がある素材は、雨で濡れると重くなります。また、布系素材は汚れやすいため、注意が必要です。
垂れ幕にターポリン素材を使うメリット・デメリット
メリット
ターポリン素材は耐久性が高く、風雨や直射日光にも強い性質があります。そのため、屋外に常設することも可能です。
デメリット
ターポリン素材の垂れ幕は厚みがあり、折りたたみにくいため、丸めて保管する場合が多いです。重さもあるため、持ち運びには向いていません。また、垂れ幕の素材としては比較的高価です。
垂れ幕に「ユポ」を使うメリット・デメリット
メリット
ターポリン素材と同様に、ユポとクロス(合成繊維)を貼り合わせた「クロスユポ」は、屋外で使用するタペストリーなどの垂れ幕の素材として、よく利用されています。クロスユポは優れた強靭性を備えており、ミシン縫製や針金通しなどの加工にも対応可能です。
また、ユポには各種のワイドフォーマット印刷にも対応したラインナップがあり、大型印刷物の製作にも向いています。ユポは選挙のポスターにもよく採用され、耐水性と耐久性を評価された、屋外使用の実績が多数あります。バイオマス樹脂を配合していて、CO₂排出量削減に貢献できる「ユポグリーン」シリーズも、選択可能です。塩化ビニール樹脂を使用しておらず、廃棄焼却する際に有害な塩素系ガスが発生しません。ターポリンと比較すると安価であり、費用面から選択される場合も多いです。
デメリット
ターポリン素材と比較すると、ユポは耐久性で劣る場合があります。
垂れ幕素材の使用可能期間の目安
布系素材の垂れ幕
トロマットやポンジなどの布系素材の使用期間の目安は、屋内では1~2年、屋外では3か月~半年と言われています。陰干ししてよく乾燥させた上で、湿気や直射日光を避けて保管すると、長持ちします。濡れたまま保管すると、寿命が短くなるため注意しましょう。
塩化ビニール系素材の垂れ幕
塩化ビニール系素材の代表であるターポリンの使用期間の目安は、屋外では1~5年と言われています。ただし、設置場所の天候、温度、日照条件などの外部要因によっても、使用できる期間は変動します。保管する場合は印刷面を内側にして筒状に丸め、冷暗所に置きましょう。折りたたんで、印刷面同士が接するように保管すると、インキが剥がれる可能性があります。
垂れ幕を製作するときに気をつけるべきポイント
ここでは、垂れ幕の素材を選ぶ際の注意点や、製作時に気をつけるべきポイントなどを解説します。
使用する環境を考えて素材を選ぶ
垂れ幕の素材は、使用する場所の環境に合わせて選ぶことが大切です。屋内と屋外では、適する素材が異なります。また、風雨の強い場所なのか日光がよく当たる場所なのかによっても、適切な素材が異なるため、注意しましょう。
使用期間を考えて素材を選ぶ
垂れ幕の素材を選ぶ際は、垂れ幕を使う期間も考慮する必要があります。短期間の使用と長期間の使用では、向いている素材が異なります。また、短期間使った後に再利用するかどうかや、何年も継続して使用したいかどうかによっても選ぶべき素材は変化するため、注意しておきましょう。
垂れ幕の大きさにハトメの数を合わせる
垂れ幕の大きさに合わせ、適切な数のハトメを設ける必要があります。ハトメとは、紐を通す穴を補強する部材を取り付けることです。垂れ幕の大きさに対してハトメが少なければ、1つのハトメに大きな負荷がかかり、素材の劣化も早くなります。また、強風で破れる可能性が高くなるでしょう。
垂れ幕素材に必要な加工の種類
垂れ幕素材に必要な加工として、ハトメと袋縫いがあります。袋縫いとは、生地を折りたたんで筒状に縫製することです。また、布生地には切断面の縫製、ビニール素材には切断面の熱加工などがあります。
垂れ幕の用途と素材選び
ここでは、垂れ幕の用途とともに、それぞれでの素材選びのポイントを解説します。
商業施設
垂れ幕は、ショッピングモール、商業施設、店舗などでの宣伝によく使われています。人目に付くところに設置され、風雨にさらされる場合も多いです。そのため、垂れ幕が風であおられにくくするために、重りなども設置する必要があります。
公共施設
学校や役所などの公共施設においても、情報を掲示するために垂れ幕が使用されます。長期間継続して垂れ幕が設置される可能性が高く、耐久性の高い素材が向いています。風や日光に強い素材がおすすめです。
建築現場
建築現場では、安全を促す注意を掲示するために垂れ幕が活用されています。長期間掲示される場合が多いです。また、風が強い場所では、風に垂れ幕がたなびく音に対して苦情が出る恐れもあります。そのため、穴が開いており風を通しやすいメッシュターポリンなどが適しています。
垂れ幕にオススメな素材「ユポジェット」や「クロスユポ」
垂れ幕の素材としては、「ユポジェット」がおすすめです。フィルム素材で丈夫なため、紙素材と比較して長持ちします。各種のインクジェット印刷にも対応しています。植物由来樹脂を配合している「ユポグリーン」シリーズもあり、環境への配慮も可能です。また、ユポの強度を一層強化した「クロスユポ」もおすすめです。
まとめ
垂れ幕の素材には、布系素材と塩化ビニール系素材、ユポがあります。それぞれ特徴が異なるため、用途や使用期間などを考慮して選択しましょう。
株式会社ユポ・コーポレーションは、合成紙「ユポ」の製造販売を行っています。高い機能性を備えながらも、環境負荷の少ない点が、合成紙「ユポ」の強みです。国内No.1のシェア※を誇り、50年以上の実績があります。またユポは、セキュリティラベルの基材としても良く活用されています。転移タイプ・非転移タイプ・ぜい質タイプ、それぞれに向いた特性のラインナップがあることが特徴です。
※...合成紙市場における販売量(t)、(参考)矢野経済研究所「2022年版 特殊紙市場の展望と戦略」
「ユポ」は、脱プラスチックが難しい場合でも、プラスチック削減に貢献できる素材です。「ユポグリーン」シリーズは植物由来樹脂を配合しています。どちらも化石燃料由来のプラスチック使用量やCO₂排出量の削減につながる「環境負荷削減に貢献できる素材」としておすすめします。環境に配慮した素材をお求めの際は、ぜひお問い合わせください。
※「ユポ」「ユポジェット」「ユポグリーン」「クロスユポ」は株式会社ユポ・コーポレーションの登録商標です。
この記事を書いた人株式会社ユポ・コーポレーション
地球と人を大切にしていきたい。
当社はこれからも環境保全や環境負荷の削減を使命として社会に貢献していきます。



